|
パーソナルプラン

正解 3
この辺の問題は、常識で解答してしまいましょう。過去問を何回分かやっておけば十分かと思います。

正解3
問題文中に、「税理士資格がなければ税理士業務をおこなってはならない」と記されています。プラスしてこれも覚えておきましょう。
「ただ(無料)」でも駄目です。
税の一般的な知識を述べることやおおまかな例をもちいての税額の概算値の計算は、税理士資格がなくてもおこなうことができます。「具体的なことはただでもだめ!」と覚えておきましょう。

正解4
可処分所得とは、自分で処分可能な所得のことです。つまり、収入のうち自分でつかえないものを差し引けば解答できます。自分でつかえないものとは、税金や社会保険料のことです。したがって、
収入金額=800万円(200万円+600万円)
税金・社会保険料=196万円(96万円+100万円)
可処分所得=800万円−196万円=604万円となります。
このあたりは、わざわざ難しい言葉を使って覚える必要はありません。文章で書いていますから、このぐらいにしていますが、自分の理解のためであればもっと口語に崩して覚えてもかまいません。

正解1
労働者災害補償保険についての出題です。ここまでは、試験範囲が広すぎて手がまわらなかった方も多いのではないでしょうか。間違えてもそれほど悔やむ必要はありません。次回の試験対策として覚えるなら、次の点がお勧めです。
・1人でも労働者(パート、アルバイト含む)を使用する事業所は労災保険に加入する義務がある。保険料については、全額事業主負担となります。
・業務上災害の留意点として、休憩時間中であっても業務遂行性が認められる場合は労災保険の対象となる。
・通勤中のケガについては、労働者が就業に関し、住居と就業所との間を合理的な経路および方法により往復していることが原則的な条件となる。
・労働災害に対する保険ですから、保険料は業種によって異なる。また、災害の発生率によって同一業種であっても一定の範囲で保険料率が上下する制度もある。
・労災保険の対象となるケガや病気で治療を受けた場合、自己負担額はありません!全額保険から支払われます。
労働者災害補償保険については、ここまで覚えていれば十分です。それよりも社会保険は、老齢年金に力を注いでください。

正解1
国民年金に関する問題です。このあたりはよく出題されますから、しっかり準備しておきたいところです。
まず、国民年金の保険料についてですが、この金額は絶対に覚えておくべきです。毎年金額が変わっていくので出題されやすいのです。平成19年度価額は、月額14100円です。2・3・4の選択肢はどれもてきとうな記述です。第一号被保険者、第二号被保険者、第三号被保険者がそれぞれどういう人が対象なのか覚えていれば迷うことなく正解を選ぶことができると思います。以下の点が頭にはいっているかいま一度確認しておいてください。
第一号被保険者
自営業者(個人事業主)・農業者・学生等(2号、3号被保険者に該当しないすべての者)
第二号被保険者
サラリーマン、公務員、OL等の厚生年金保険の被保険者、共済組合組合員。
第三号被保険者
厚生年金保険の被保険者、共済組合組合員によって生計を維持されている配偶者。代表例は、サラリーマンの妻である専業主婦。

正解2
老齢年金に関する出題です。たいてい学科問題で2問、実技で問題で1問は出題されますから、老齢年金は、手を抜かずにしっかり学習しておいてください。
とりあえず、今年、60歳となる男性の定額部分、報酬比例部分の支給開始年齢は絶対に覚えておきましょう。
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの男性の場合、60歳から報酬比例部分、64歳から定額部分が支給されます。
加給年金は、配偶者が65歳になるまで支給されます。65歳以降は、加給年金は、振替加算として、配偶者の老齢基礎年金に上乗せ支給されることになります。ですから、選択肢2が誤りです。
選択肢3は少し難しい記述です。雇用保険との供給調整が出題されています。記述の通り、老齢厚生年金の支給が停止されますが、次回の2級FP技能士試験対策として覚えるなら、老齢年金と障害年金や遺族年金との供給調整を覚えておいた方が良いと思います。
選択肢4はひっかけ問題です。支給停止になるのは、定額部分です。

正解4
遺族年金に関する問題です。遺族年金・障害年金あたりは、老齢年金についで出題されますし、概要だけおさえる程度でも押さえておくと正解肢が選べたりしますから、ざっとで良いので見るだけはみておきましょう。
遺族年金については、基礎と厚生の違いは良く出題されます。遺族基礎年金は、死亡した者と生計維持関係にあった子または子のある妻に支給されます。「基礎=子がいないともらえない」と覚えておいてください。
遺族厚生年金は、生計維持関係にあった妻、夫、子、父母、孫、祖父母に支給されますが、通常、2級FP技能士/AFP試験では、妻、夫、子ぐらいまでしか聞かれません。基礎との違いがわかっていれば十分だと思います。
寡婦年金の支給額は、夫が生きていた場合に受給できた老齢基礎年金額の3/4となります。選択肢2は、知らないと答えられませんが、3/4という数字は、遺族厚生年金の年金額の計算(老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4)にもでてきます。できれば覚えておいてください。
選択肢4については、死亡一時金と寡婦年金が同時に受給できる場合は、どちらかを選択することだけ覚えておいてください。ときどき出題される記述です。

正解4
国民年金基金は、自営業者などの20歳以上60歳未満の第一号被保険者が加入することのできる老齢基礎年金の上乗せ制度です。選択肢1は、年齢と加入者が2重に間違っています。
基金の種類は、終身年金の2種類と確定年金の3種類の計5種類ですが、一口目は、必ず終身年金のうちいずれかとしなければならないことになっています。
国民年金基金については、もう一点、今回出題はありませんでしたが、掛け金には上限があり、原則として月額68000円が限度、個人型確定拠出年金にも加入している場合は、あわせて68000円が限度となることを覚えておきましょう。
小規模企業共済とは、一定規模未満の中小企業の経営者、役員のための退職金の準備制度です。従業員のためではありません。退職金に対する課税の扱いは、選択肢4のとおりです。2級FP技能士試験において最重要科目である「所得税」に関する部分はきっちり押さえておきましょう。

正解2
パーソナルプランの問題のはずですが、これは所得税の問題です。いかに所得税が重要科目であるかよくわかります。
選択肢1は、でたらめの記述ですから気にする必要はありません。
個人型確定拠出年金の掛け金は、小規模企業共済等掛け金控除の対象となります。小規模企業共済等掛け金控除については、試験対策上、これしか覚えるところがありませんよ・・・。
損害保険料控除については、原則廃止となりました。ただし、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険については、経過措置としてH19年以降も損害保険料控除が適用できます。
変額個人年金保険は、通常、生命保険料控除の対象となります。個人年金保険料控除の適用を受けるためには、個人年金保険料税制適格特約を付加していること等の条件があり、該当するものだけが対象となります。よくあるひっかけですね。

正解2
財形住宅貯蓄の利子等非課税限度額は、550万円までとなります。保険型は、385万円までとなるのは財形年金貯蓄の場合です。
相続時精算課税制度の贈与者は、自分の親(父・母)であることが条件です。
住宅ローン控除は、原則的には、所得税から控除されます。ただし、平成11年から平成18年までに入居したものに限り、今まで所得税から控除されていた分が控除しきれなくなった場合、申告により、平成20年度分以降の住民税の所得割額からも控除する経過措置が設けられています。
居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除と住宅ローン控除の供用は認められています。居住用に関する特例は、よく出題されますから、その他の特例の留意点もチェックしておいてくださいね。
  

☆ 2級FP技能士/AFP試験 実技試験対策 問題集のご案内
 
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 合格応援! 2級FP技能士/AFP試験対策 問題集のご案内
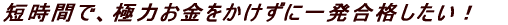
 
ステップアップ問題集 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ FP技能士/AFP試験対策 合格応援シリーズ 第2弾!何が変わった!?2012年改正ポイントかんたん解説Bookのご案内
 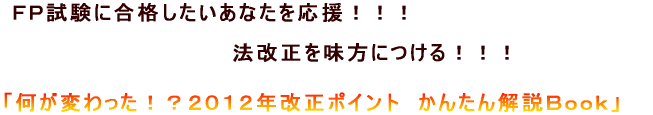
無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験対策 学習補助ツールのご案内
2級FP技能士/AFP試験対策専用テキスト 「 超 抜 粋 」
「 超 抜 粋 」は、FP試験の最重要ポイントのみを抜粋した試験対策専用のテキストです。ご利用の際は、利用上の注意点をよく読んでいただいた上でご活用いただきますようよろしくお願いいたします。
「 超 抜 粋 」 詳細 ・無料サンプル・ご利用上の注意点は、こちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP試験 学習補助ツール
 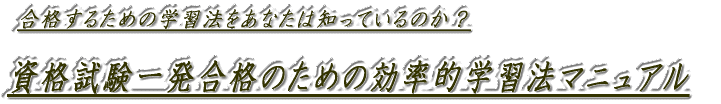
効率的学習法マニュアル 無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!

☆ 2級FP技能士/AFP対応テキスト販売のご案内
 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に 本当にあった!2級FP技能士/AFP試験に
きっちり合格できるテキスト+ステップアップ問題集をまとめてダウンロード! 
無料サンプル登場!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらのテキストをご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト内容についての質問等については、次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。


 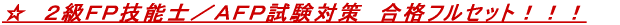 
各商品の無料サンプルあり!もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック!
☆ こちらの商品をご購入いただけた方に限り、メールでのテキスト・問題集等内容についての質問について次回試験日前日まで何回でもお答えさせていただきます。ただし、返信が遅れる場合もございますことご了承ください。
特定商取引法に基づく表記 個人情報保護方針
 HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ HP・メルマガ・テキスト販売に関するお問い合わせ


|
本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2013年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
| ![]()

